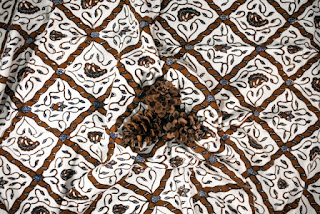熱中症対策に取り入れては?東南アジアの”清熱”飲料
中華系の食材店やレストランなどでよく見かける、ライチ、菊の花、冬瓜、胡瓜、など日本人にもわかる中国語と、ナチュラルなデザインのソフトドリンク 。マレーシアやシンガポールに行ったときはジャカルタよりももっと頻繁に見かけた。 ”清熱”とあるからスッキリさわやかな味だろうと思って早速試してみたら、甘すぎてスッキリするどころか却って喉が渇いて普通の水が飲みたくなってしまった。現地の消費者の好みに合わせたものだから缶入りのものが甘すぎるのは仕方ないけれど、こういう伝統的な飲み物が、暑い国で暮らす長い間の人々の生活の知恵から生まれたものであるということについては間違い。 そもそも日本人には、身体は温めた方がいいもので、からだの中の熱をとることが大切だという感覚がないので、こういう伝統的な清涼飲料って何のために飲むものなのかよくわからない。 漢方によれば、温めるだけでなくバランスを取ることが大事。喉の痛みや口内炎、夏バテのような症状は、身体の中に過剰な熱が溜まることで、炎症をおこしているためなので、清熱作用のあるものを摂取して、からだの中の熱をとるということが重要なのだそうだ。 ”清熱作用”を意識した伝統的な飲み物やデザートが数多いということは、東南アジア何処へ行ってもでも結構共通している。特に各地に散らばっている中華系民族の間では 共通の伝統的レシピが維持されている。 菊花茶など複数の薬草を煮出したお茶やこれを寒天で固めたもの、瓜や果物の他にも、黒もち米や大麦、白クラゲとか、ナツメやクコの実ハスの実など、乾物を煮出して砂糖で味付けするといったデザートが多い。 インドネシア現地発の”清熱ドリンク”はジャムウと呼ばれ、地方によってさまざまな自然の材料が薬として飲用されている。スーパーやコンビニ、全国どこでも売ってるもっともポピュラーなものでいうと、カキティガという謎の飲料がある。 水と同じ透明な液体、ボトルのデザインは、緑色のサイのイラスト。これではいったいどんな飲み物なのか、想像もつかないけれど、じつはこれは漢方の生薬である石膏のミネラル成分が主な成分で、これも清熱作用のために飲むものだ。 水よりものど越しが重い感じがするくらいで、基本、味も香りもないから、ソフトドリンクというより薬みたいな感じ。なんかのどが痛くなりそうだなというとき、喉が痛いとき、ペットボトル入りのものは特に水...